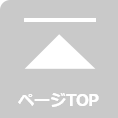ポイントプログラムとのかしこいつきあい方
- 日本経済大学 経営学部
教授 寺地 一浩(てらち かずひろ) - コンビニやスーパー、家電量販店をはじめ航空や鉄道、電気料金等…私たちの生活に関わるさまざまな企業が、ポイントプログラム(ポイントカード)に取り組んでいます。ポイントプログラムは、もはや私たちのくらしに欠かせない存在となっています。
「どのようにポイントがもらえるか」で、時には私たちの行動にまで影響を与えるポイントプログラム。運営する企業と私たち消費者の視点から考えていきましょう。

ポイントプログラムとは
ポイントプログラム(ポイントカード)は、1980年代に米国の航空会社がマイレージプログラムとして導入したことが始まりです。
商品を購入したり、サービスを利用した時に、お店や企業からスタンプを押してもらったり、シールをもらい、貼って貯める紙のポイントプログラムの時代から、財布やカバン等に入れて持ち歩くポイントカードを経て、現在はインターネットショッピングの拡大もあり、スマートフォンやインターネット上で貯められる、ポイントプログラムに発展してきました。
商品購入やサービスを利用した特典として、さまざまな企業がポイントを提供しています。貯めたポイントが、もらった特定の企業でしか使えないものから、共通ポイントといって、異なる企業でポイントを使えるもの、またインターネット上で貯めたポイントを交換できるものまであり、貯めたポイントの使い勝手も、私たちが使用しやすい仕組みになってきています。
企業側のメリットは?
ポイントプログラムを運営する企業は、ポイントを消費者に付与(与える)することにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。
第一に、スタンプやシールといった、ポイントプラグラム初期の時代から変わらないことですが、消費者との長期間の良好な関係を築けるというメリットです。つまり、顧客を捉えて離さないように固定化を目指す「顧客の囲い込み」と、ポイントを貯めることで、より企業に愛着を持ち、多くのものを買ってもらうことを目指す「優良顧客化…企業から見た、利益をもたらす優良な顧客を育てること」です。
第二に、ポイントプログラムにより、消費者の氏名、性別、年齢などの個人情報や購買情報を収集して消費者を識別し(見分ける)、収集した情報をマーケティングに活用できるメリットです。
例えばポイントプログラムがなければ、企業は取引する消費者の中で、どの消費者が利益をもたらす優良顧客で、どの消費者が利益の少ない特売品だけを買う顧客かを、見分けることができません。
企業は消費者を選別することで、企業に愛着を持って利益をもたらす優良顧客に対応したマーケティングを行うことが可能になり、顧客ロイヤリティ(愛着や忠誠心)を高め、ライバル企業との差別化を図っていくことを目指しています。
運営する企業側の課題
現在、ポイントプログラムを運営する多くの企業が、課題に直面しています。それというのも、多くの企業は、同じようなポイントプログラムを運営しており、ポイントを付与するだけでは他社と差別化できないこと、収集した情報をマーケティングに効率的に活用できていないからです。
ポイントをたくさん付与するにはコスト面での限界があり、多くの企業では、消費者に恩恵を提供する手段としてしか、ポイントプログラムを活用しきれていない状況です。
ポイントプログラム運用のメリットを活かすには、収集した情報をいかにマーケティングに活用するかが、今後、企業に期待されるところです。
消費者の不思議な行動
私たちは、日々の生活の中で、ポイントプログラムを、どのような存在として捉えているのでしょうか。
これまでの多くの調査では、「ポイントがもらえるかどうか」「どのようにもらえるか」が、私たちの消費行動に影響を与えていると、指摘されています。ポイントに興味を持ち、執着することや、またポイントを貯めることに喜びを感じることは、私たちの多くが経験していることだと思います。
これらポイントに対する消費者の「不思議な行動」について、その全てが解明されているわけではありませんが、行動経済学に着目して、心理的な影響を受けた2つの「不思議な行動」について読み解いてみましょう。
行動経済学とは、伝統的な経済学ではうまく説明できなかった人間の不思議な経済行動等について、人間の心理や行動の癖から傾向を明らかにして経済現象を理解していこうとする学問です。
①貯めることに執着してしまうのは、なぜ?
私たち消費者のポイントについての認識は、心理的な効果が存在して、貯めることに執着する行動に影響していると考えられます。というのも、私たちの多くは、ポイントを企業通貨として重要な価値だと思い、お金(貨幣)の役割の一部を担っていると認識しています。また同時に、商品やサービスを利用した時の特典・報奨としても認識しています。
これらのポイントの価値を検証した研究結果より、お金(貨幣)と違って、ポイントには心理的な効果の一つである賦存効果(ふそんこうか)が存在することがわかっています。
賦存効果とは、損失回避性がもたらす影響の一つで、同じものであっても、自分が保有しているもの(財産など)は、自分が保有していない場合より、高く評価する傾向のことです。
この効果により、一度自分のものになったものは手放そうとせず、また手放す場合は損失の痛みを感じることになります。
ポイントを重要な価値だと思い、さらにはお金(貨幣)と同様ではないという認識が、心理的な効果となって、ポイントを手放そうとせず、貯めることに執着する消費行動に影響を与えていると考えられます。
②ワクワクするポイント○倍?
企業がポイントを付与する時の表現の仕方によって、私たちの行動が心理的に影響を受けることがあります。
例えば、ドラッグストアやスーパー、家電量販店では「ポイント○倍」のポイント「倍付」のセールと、「ポイント○%」のポイント「○%付」のセールがよく行われています。
これらの2つのポイント付与で(経済的にはもらえるポイントはどちらも同じ場合)、私たち消費者が買いたいと思う「購買度」を検証した研究結果によると、「ポイント○倍」の方が「ポイント○%」に比べ、購買度が高いことがわかっています。
これは消費者の心理的な効果の一つであるフレーミング効果による影響です。
フレーミング効果とは、同一の内容のものであっても表現の仕方により、消費者の意思決定に様々な影響を及ぼす効果のことです。
経済的には、もらえるポイントは同じでも、消費者は「ポイント○倍」の方が、「通常ポイント」を基準に何倍かを具体的に思い浮かべやすく、購買度が高いと考えられます。
このフレーミング効果は、ポイント付与の表現だけではなく、私たちの消費生活のさまざまな場面で見られる心理的な現象です。
かしこいつきあい方とは!
それでは、時に不思議な行動を取る、私たち消費者のポイントプログラムとのかしこいつきあい方について考えてみましょう。
●多くの種類のポイントを貯めるより、よく利用するポイントを集中して貯めましょう。
- 多くのポイントプログラムには優良顧客を対象としたポイントのランクアップやサービス特典があります。集中して貯めることにより、優良顧客として対応されます。
- ポイントをもらっても、ポイント交換ができる単位まで貯まらないケースがあります。集中してポイント残高管理を行うことによりポイント交換漏れを防ぐことができます。
●ポイントセール時の利用や、ポイントプログラムの入会は、いったん立ち止まって考えてから、行動しましょう。

- 「ポイント○倍」や「50ポイントプレゼント…」などのポイントセールでは、もらえるポイントを金額換算し、納得(できればポイント交換をイメージ)してから行動しましょう。
- ポイントの盗難事件や、個人情報流出事故も考えられます。むやみにポイントプログラムに入会して個人情報を提供するより、よく利用するポイントプログラムに集約した方が、個人情報の管理面や年会費負担でもメリットがあります。
私たちは、ポイントを貯めることに喜びを感じるなどの心理的な効果があることを認識した上で、いまやくらしの中で欠かせない存在となったポイントプログラムとの、かしこいつきあい方を目指していきましょう。



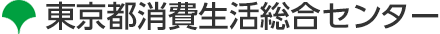

 トップページ
トップページ 今月の話題
今月の話題 図書資料室から
図書資料室から 安全シグナル
安全シグナル お知らせ
お知らせ 講座案内
講座案内 情報ピックアップ
情報ピックアップ 相談の窓口から
相談の窓口から フレッシュ市場
フレッシュ市場 TOKYO景観探訪
TOKYO景観探訪