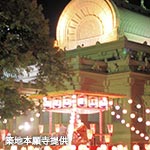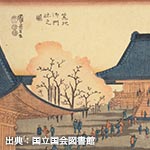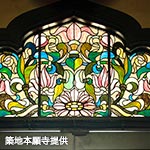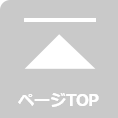唯一無二の世界が広がる、築地のシンボル
中央区築地三丁目に建つ、一風変わった佇まいの築地本願寺。「お西さん」こと浄土真宗本願寺派の直轄寺院で、本堂・石塀・三門門柱(正門・北門・南門)は国の重要文化財に指定されている。設計は、日本建築史の創始者で建築家の伊東忠太。古代インド仏教様式をモチーフにした鉄筋コンクリート造で、1934(昭和9)年に竣工。周囲の街並みは戦災や高度経済成長期以降の開発で大きく変わったが、この寺院が生み出す独特な景観は失われることなく、長く人々に愛されている。
創建は江戸時代初期の1617(元和3)年にまでさかのぼる。当時は横山町(現在の中央区日本橋横山町)にあり、浅草御堂と呼ばれていた。しかし1657(明暦3)年、江戸城を含む江戸の大半を焼き尽くした「明暦の大火」(振袖火事)により全焼。元の地での再建はかなわず、替え地として幕府が用意したのが、現在、築地本願寺が立っている場所である。しかし当時のこの地は海だったため、門徒が中心になって埋め立てて土地を築き、寺院を再建したのだ。ちなみにそれが、「築地」の地名の由来となっている。
この時の本堂等は現在と全く違う趣で、江戸後期の浮世絵師・歌川国芳の作品(下の絵図参照)などに描かれているとおり、伝統的な寺院建築であった。それが1923(大正12)年の関東大震災で再び本堂を焼失。その11年後に竣工したのが、現在の建物である。伊東忠太ならではの意匠といえる石造りの動物や妖怪が本堂の入り口などに点在し、探し歩くのも楽しい。さらに、寺院には珍しいステンドグラスやパイプオルガンがあり、由緒正しい寺院でありながら、唯一無二の世界が広がっている。
- 所在地
- 中央区築地三丁目15-1
- 建設年
- 昭和9(1934)年
- 設計
- 伊東忠太
- 規模
- 2階建(本堂)
- 最寄駅
- 東京メトロ日比谷線「築地」駅から徒歩約1分、または同・有楽町線「新富町」駅から徒歩約5分。都営地下鉄浅草線「東銀座」駅または同・大江戸線「築地市場」駅から徒歩約5分


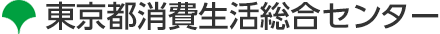

 トップページ
トップページ 今月の話題
今月の話題 図書資料室から
図書資料室から テストレポート
テストレポート 東京都消費者被害救済委員会報告
東京都消費者被害救済委員会報告 情報ピックアップ
情報ピックアップ お知らせ
お知らせ 講座案内
講座案内 相談の窓口から
相談の窓口から フレッシュ市場
フレッシュ市場 TOKYO景観探訪
TOKYO景観探訪