- ページ内を移動するためのリンク
- 本文(c)へ
- グローバルナビゲーション(g)へ
- ローカルナビ(l)へ
- サイトのご利用案内(i)へ
トップページ > 商品安全 > 東京都商品等安全対策協議会 > 「ベビー用のおやつ」の安全対策について > ベビー用のおやつの安全対策についてを報告
更新日:2013年3月21日
ベビー用のおやつの安全対策についてを報告
平成21年1月28日
生活文化スポーツ局
「ベビー用のおやつ」による窒息に注意しましょう!
東京都商品等安全対策協議会報告 ~「『ベビー用のおやつ』の安全対策について」~

東京都商品等安全対策協議会は、報告書「『ベビー用のおやつ※』の安全対策について」を、本日、東京都に提出しました。報告書の主な内容は次のとおりです。
※「ベビー用のおやつ」とは、「○ヶ月頃から」などと乳児(1歳未満の子供)を対象とうたったソフトせんべい、ビスケット、ボーロ、ウエハース等の乾燥した菓子類をいう。スーパーマーケット、薬局・ドラッグストア等で多種多様な商品が販売されている(写真参照)。
1 報告書の主な内容
(1) 「ベビー用のおやつ」による窒息事故に関する調査結果
インターネット消費者アンケート調査等により、潜在化している窒息事故の状況等が明らかになった。
ア 与えていた世帯が95.4%。
イ 危害またはヒヤリ・ハットの経験は5人に1人以上(図1及び2参照)。
ウ どこにも相談しない人がほとんど(97.5%)。
エ 購入する際、対象月齢表示を参考にする人が8割以上。
オ 注意表示を読まない人が3割以上。
カ 与えた理由で多いのは、「子供がよく食べるからまたは欲しがるから」や「外出時やぐずった時に便利だから」。
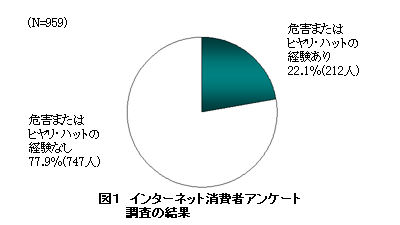
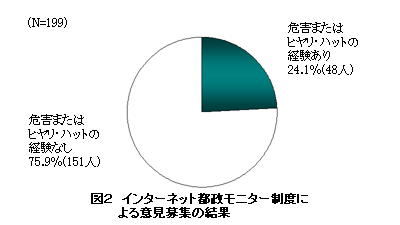
(2) 「ベビー用のおやつ」における現状及び課題
ア 各社の規格はあるが、業界内で統一化されていない。国が定める「授乳・離乳の支援ガイド」(参考1参照)と比較すると、対象月齢が早い商品が一部ある。また、商品に記載されている注意表示がわかりにくい。
イ 多くの消費者が1歳未満から与えている。離乳食に関する食育の不足が懸念される。注意表示を読まない消費者もいる。
ウ 事故情報の潜在化により、消費者の声が届かず、商品の改良につながらない。
(3) 「ベビー用のおやつ」の安全対策に係る提言
ア 「ベビー用のおやつ」の安全対策の実施
(ア) 商品の注意表示の改善
(イ) 「ベビー用のおやつ」の安全性に関するガイドライン等の策定検討
(ウ) 食品による窒息事故防止のための定期的かつ継続的な調査・研究の実施
イ 消費者への普及啓発
(ア) 食育の視点に立った普及啓発
(イ) 乳児健康診査時の保護者への普及啓発
(ウ) 母子健康手帳への反映
(エ) 東京都及び事業者による消費者への積極的な情報提供・注意喚起
2 東京都の対応
(1) 国や関係する団体等への提案・要望
国(厚生労働省及び内閣府)に対し、窒息事故防止のための定期的かつ継続的な調査・研究の実施及び母子健康手帳への反映について提案します。また、関係する団体に対し、「ベビー用のおやつ」の安全性に関するガイドライン等の策定検討等について要望します。
| 宛て先 | 内容 | |
|---|---|---|
| 提案 | 厚生労働省 医薬食品局食品安全部 |
|
| 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 |
|
|
| 内閣府 食品安全委員会 |
|
|
| 要望 | 日本ベビーフード協議会 |
|
| 全日本菓子協会 |
(2) 消費者への注意喚起
ア 子供の成長には個人差があります。「ベビー用のおやつ」は、表示されている月齢のみを参考にするのではなく、子供の様子を見て食べさせましょう。また、食べさせる前に、子供にとって、本当に必要なのか考えましょう。
イ 窒息事故防止のために、商品に表示されている注意にしたがって食べさせましょう。
ウ 万が一、食品などにより窒息した場合の対処法について理解しておきましょう(参考2参照)。
今後、リーフレット、ホームページや情報誌等を用い、注意喚起等を行う予定です。
別紙:「授乳・離乳の支援ガイド」・「窒息した場合の対処法」
参考資料1:東京都商品等安全対策協議会の概要
参考資料2:「ベビー用のおやつ」の安全対策について~東京都商品等安全対策協議会報告書の概要~
報告書(全文):「ベビー用のおやつ」の安全対策について
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055