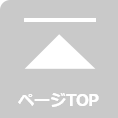震災と戦災の犠牲者を弔う都選定歴史的建造物
大正12(1923)年9月1日に起きた関東大震災は、関東全域で死者・行方不明者合わせて約10万5千人という甚大な被害をもたらした。東京都慰霊堂は、東京市(当時)での遭難死者約5万8千人の遺骨を納めるために建てられた施設であり、当初は「震災記念堂」といった。築地本願寺や明治神宮などを手がけた建築家・伊東忠太が設計し、昭和5(1930)年の竣工。本堂は寺院風のデザインだが、鉄筋コンクリート造で耐震・耐火構造をうたっている。本堂の屋根や講堂入口の上方には、伊東の作品の特徴である妖怪の彫像(下写真参照)を確認できる。
震災時、この場所では3万8千人ほどが亡くなっている。もともとこの地にあった陸軍被服廠が赤羽に移転したため、東京市は跡地を買収して公園の造成を進めていた。そこへ大地震が起こり、下町地域は焦土となるような火災に見舞われた。周囲に住む4万人近くが空き地であったこの地に家財道具を携えて避難してきたが、大規模火災の炎と台風の影響による強風が合わさって「火災旋風」となって人々を襲ったのだ。
さらにこの地域は太平洋戦争末期、昭和20(1945)年3月10日の「東京大空襲」など、米軍の爆撃に何度もさらされ、震災時よりもはるかに多い犠牲者が出た。10万5千人分という膨大な数の身元不明遺骨を合葬し、昭和26(1951)年には施設の名称も東京都慰霊堂と改められた。
毎年9月1日と3月10日には、当施設に納められている震災と戦災による多大な犠牲者を弔うため、大規模な慰霊大法要が催されている。震災から94年、戦災から72年の時が過ぎたが、風化させることなく次代に伝える役割を、この施設は果たしているのである。
- 所在地
- 墨田区横網二丁目3-25(都立横網町公園内)
- 建設年
- 昭和5(1930)年
- 設計
- 伊東忠太
- 規模
- 地上3階(三重塔)
- 最寄駅
- 都営大江戸線「両国」駅、JR総武線「両国」駅


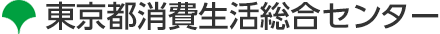

 トップページ
トップページ 今月の話題
今月の話題 図書資料室から
図書資料室から 高齢者悪質商法被害防止キャンペーン
高齢者悪質商法被害防止キャンペーン 安全シグナル
安全シグナル お知らせ
お知らせ 講座案内
講座案内 相談の窓口から
相談の窓口から フレッシュ市場
フレッシュ市場 TOKYO景観探訪
TOKYO景観探訪