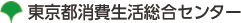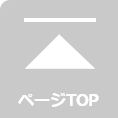![●有料老人ホーム ※本稿では介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム及び自立型有料老人ホームを指します
[介護型]・介護付き有料老人ホーム … 施設の職員から直接介護サービスを受ける ・住宅型有料老人ホーム … 介護サービスは外部に委託
[自立型]・自立型有料老人ホーム … 介護認定を受けていない時から入居する有料老人ホーム
●サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) … 安否確認と生活相談の基本サービスが付いた住宅賃貸借契約が多い
●シニアマンション … 高齢者向けの設備やサービスを整えた分譲マンション入居者の年齢制限を設けている場合が多い](images/wadai/img_1.png)
誰もが想定以上に長生きをする時代になりました。高齢者の一人暮らしが増加する中で、要介護高齢者も増え続けています。自宅での暮らしが出来なくなった時に、高齢者住宅に住み替える人が増えていますが、サービス内容など納得できるまで確認する必要があります。特に、主に民間企業が供給する有料老人ホームなどの高齢者住宅は、サービスや契約形態などの面でさまざまな違いがあります。こんなはずではなかったという後悔をしないために、その違いを知っておきましょう。
介護保険と高齢者住宅
介護保険法が制定されて18年が経ちました。高齢者住宅を選ぶ時に気を付けたいことは、介護保険サービスがどう利用できるかです。最期まで介護が必要にならずにすめば、これほど幸せなことはありませんが、多くの人は何らかのサービスを使わざるを得ません。
民間の高齢者住宅の主な種類
民間企業などが供給する高齢者住宅には、「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「シニアマンション」などがあり、それぞれ法律や制度によって住み心地が全く違います。今回は各住宅の違いについて、その特徴や契約形態(権利方式)、サービス内容等を中心に解説します。
①有料老人ホーム
昭和38年に制定された「老人福祉法」第29条に定義されている老人ホームで、元気な時から入居する「自立型」(それほど数は多くないため、本稿では詳述はいたしません)と介護サービスが必要になってから入居する「介護型」があります。「介護型」の有料老人ホームは、介護保険の利用方法によって「介護付き有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」に分かれます。契約前には面談があり、健康診断書の提出も必要になります。
(ア)介護付き有料老人ホームは、介護保険法に基づき「特定施設入居者生活介護※」の指定を受け、自宅での暮らしと変わらない生活を支援するホームです。介護保険をホーム内で100%使い切ってしまうと考えるので、ホームに支払う介護費用は定額(要介護度により変わる)になります。介護度が変化しない限り介護費用は一定ですから予算も立ちます。24時間、ホームの職員からサービスを受け、その職員数は入居者3人に対して介護・看護職員1人以上となっています。
(イ)住宅型有料老人ホームは、ホームの入居契約と介護サービスの契約は別になり、自分が受けたいサービスを選び、介護計画(ケアプラン)を立てて利用します。介護費用は、介護保険で定める1か月の利用限度額以内であれば、1割負担(2割、3割の人もいます)ですみますが、限度額を超えると超えた分は全額自己負担になります。
※特定施設入居者生活介護:介護・看護職員配置等の一定の基準を満たし、都や区市町村の指定を受け、居住者に介護サービスを提供するもの
②サービス付き高齢者向け住宅(以下、「サ高住」といいます。)
平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の見直しで「住まい」と「ケア」を分離した高齢者向けの住居で、その多くが賃貸住宅です。日中はフロントに職員が常駐し、安否確認と生活相談のサービスを行っています。しかし、介護を含めたその他全てのサービスは、外部と契約して利用します。また、サ高住の約5%は特定施設入居者生活介護の指定を受けており、その場合は施設の職員が介護サービスを提供します。
③シニアマンション
昭和の時代から少数ですが入居者の年齢制限を設けているシニア専用のマンションが建ち始めました。年齢は50歳~60歳以上とさまざまですが、入居時の受け入れ年齢を80歳までとしているものもあります。シニアマンションは、後述するように分譲住宅(所有権方式)であり、居室を好きなようにリフォームできます。また、他人への売却や相続も可能です。ここで、注意したいのは、自分が住まなくなった時や、相続で譲り受けた人が住みたくなくても、所有したままだと管理費等を払い続ける必要があることです。また、売りたい時に希望する価格で売れるとは限らないというリスクもあります。それは一般の不動産業者が取り扱わないからです。
高齢者住宅の契約形態(権利方式)
高齢者住宅の契約形態は大きく3種類あります。
(1)利用権方式(有料老人ホームに多い)
利用権とは、居室と共用部分を使用する権利(居住)と各種サービスを受ける権利です。この利用権は契約者一代限りの権利で、売却や相続はできません。利用権方式の有料老人ホームでは、通常、入居一時金を前払いします。これは家賃と生活サービス費の前払いに相当します。その一時金には初期償却と償却年数が定められています。初期償却とは、契約者がホームに入居した時点でホームの収入になる割合のことで、0%から30%と企業によってさまざまです。また、償却年数は、その年数で一時金がゼロになります。5年から20年と幅が広いですが、その間に退去になった場合には未償却分が返還されます。(図表1を参照)
| Aホーム | Bホーム | |
|---|---|---|
| 初期償却 | 0% | 30% |
| 入居日の預かり金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 1年目の返還金額 | 800万円 | 560万円 |
| 2年目の返還金額 | 600万円 | 420万円 |
| 3年目の返還金額 | 400万円 | 280万円 |
| 4年目の返還金額 | 200万円 | 140万円 |
「前払金の初期償却について」
東京都では「前払金は家賃等の対価であることから、前払金の初期償却は不適切である」と指針で定め、初期償却そのものを廃止するよう消費者保護の観点から事業者団体・各事業者に強く働きかけています。
(2)建物賃貸借方式(サ高住に多い)
毎月家賃を支払う賃貸住宅です。高齢者向けの賃貸住宅なので、「終身建物賃貸借契約」をとるものもあります。この契約は、途中で契約更新の必要がなく、契約者が死亡した時点で自動的に契約が終了するという特殊なものです。
(3)所有権方式(シニアマンションに多い)
通常の分譲マンションと同様に所有権を取得し、自分名義の不動産になります。しかし、シニアマンションで説明したように、売りたい時に希望する価格で売れるとは限りませんから、財産になると考えると当てが外れる場合もあります。
サービス内容の比較
高齢者住宅は、いずれ自分の身の回りのことができなくなった場合に備え各種サービスが用意されていますが、そのサービスがどのように提供されるかで、暮らし方も費用も大きく変わります。具体的なサービスには次のようなものがあります。
各種サービスの例
- ①声かけ 職員が入居者一人ひとりに気を配り、挨拶や声をかけます
- ②夜間の見守り 職員が夜間に巡回します
- ③状態把握 入居者に変化がないかどうか常時、状態を気にかけます
- ④服薬管理 看護師が薬の飲み忘れなどがないようにお世話します
- ⑤職員配置 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、一定数の職員が常駐します
- ⑥認知症対策 施設ごとに対応が異なるので契約時に確認が必要です
- ⑦食事の提供 施設で一体的に提供する場合のほか、外部の委託先から提供する場合があります
- ⑧感染症対策 届け出が必要な施設は保健所の指導のもと対策を講じます
- ⑨消防訓練等 防火管理者を置き、消防訓練・避難訓練を行います
「夜間の見守り」については、介護付き有料老人ホームでは要介護度に応じて時間ごとに入室確認する巡回がケアプランに組み込まれています。住宅型有料老人ホームの中には管理費の範囲で夜間の見守りが行われている場合もあります。
「状態把握」とは主に健康状態の確認のことです。常時食事の摂取状況や体温・血圧を測り夜間の睡眠状態など看護師を中心にチームで世話をする方法等がありますが、実際の対応は各住宅によってまちまちです。
また、特に「服薬管理」はいろいろな方法があるので、要注意です。例えば、居室に「お薬カレンダー」を作り、そこに毎日の薬を入れるだけでも「服薬管理」と言えますが、その場合は本人の飲み忘れが心配です。施設によっては、薬を健康管理室で保管・管理していて、毎食事に「食前の薬」「食後の薬」を一人ひとり飲み込むまでを確認してくれます。
このように、同じサービスでも内容に大きく相違があるのです。入居した後で、望んでいたサービスと違ったと後悔しないためには、事前に具体的なサービスの提供方法などを確認し、比較することが大切です。
備えあれば憂いなし
自分だけは大丈夫と思いがちですが、人間は必ず老います。病も自覚症状なしに突然やってきます。その時になってあわてないように、今から学習しておきましょう。自分で自分のことができなくなった時に、誰の手を借りるのか、どこで暮らすのか、早めに考えておくことが幸せな老後への道なのです。

「老人ホーム入居権」に関する買え買え詐欺
老人ホームのパンフレットが突然自宅に届き、その後に証券会社をかたる者が電話してきて、「その老人ホームは大変人気があるが、パンフレットが届いた人しか申し込みできない。代わりに申し込んでくれれば高値で買い取る」などと言ってお金をだまし取ろうとする詐欺が散見されます。不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。