ここから本文です
海外事業者が運営するインターネット通販サイトのトラブル
1はじめに
インターネットを利用して商品を購入したり、映画の視聴や音楽配信サービスを利用するなど、インターネットで提供される商品やサービスは、品揃えが豊富だったり検索が容易、自宅から手続ができるなど、大変便利です。海外の製品をインターネットから購入する生徒も多いと思います。
サイトが日本語で表示されていたり、サイトのドメイン(URL)が「.jp」などとなっていても、サイトの運営事業者は海外事業者である場合があります。また、オンラインショッピングモール(デジタルプラットフォーム)を利用して商品を購入すると、売買契約の相手方は出店事業者となりますが、出店事業者が海外事業者であることも少なくありません。
国民生活センターが運営する越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)では、海外の事業者と日本の消費者の間の消費生活相談をサイトで受け付け、メールで助言を行っています。
2023年度CCJに寄せられたインターネット取引に関する相談のうち、86.5%が日本語表示のサイトとなっています。
日本語表示のサイトは日本の消費者に向けて発信していると考えられますが、消費者はサイトの運営事業者が海外か日本かを意識せず利用することが多いと思います。トラブルに遭わないために、どんな点に注意していくとよいのか見ていきましょう。
2海外事業者とのトラブルの特徴
海外事業者の運営するサイトは、大小様々ありますが、海外事業者のサイトでのトラブル全般に言える特徴として、トラブルになった場合には、
- サイト表示が日本語でもカスタマーサービスが日本語対応とは限らない
- 日本語でやりとりができても、日本語ネイティブでないため対話が円滑に進まない
- 機械翻訳のようなメール返信になっている
- 返信が遅い
- 連絡が途絶える
など、事業者とのやりとりがうまくいかないケースが多く見られます。
このため、日本の事業者に比べ、解決に時間がかかったり、解決が難しくなることがあります。
3海外事業者かどうかを確認しよう
インターネット通販は、利用したサイトが日本語表示であるなど日本の消費者に向けたサイトである場合、日本法である「特定商取引法」の「通信販売」に当たると考えられます。この法律により、事業者名、住所等についてはサイトに掲載することが義務付けられています。事業者の情報は、「特定商取引法上の表示」「利用規約」「問い合わせ先」等に記載されています。(英語表示であれば「Terms & Conditions」(利用規約)、「Contact us」(問い合わせ先)、「FAQ」(よくある質問)などのコーナーに記載があることもあります。)
なお、悪質なサイトでは、偽りの日本の住所や代表者名を記載している場合もあり、この場合は日本の事業者とは限らないので、注意してください。
4悪質な海外通販サイトのトラブル
(1)悪質な海外通販サイトのパターン
次に、悪質な海外インターネット通販に関する相談事例を紹介します。
「音楽機器の販売サイトで注文しようと思い、商品についてメールで問い合わせると『商品は海外から発送され、支払方法は銀行振込になる』と返信があった。何の疑いもせず注文し、指定された銀行口座に代金を振り込んだが、商品は届かず、それ以降は販売サイトと連絡が取れなくなった。改めて、サイトに記載されていた住所で検索してみると、オーディオ、釣り具、衣類など様々な商品を扱う複数のサイトがヒットし、住所が使い回しされていることが分かった。支払った代金を返金してほしい。」
注文した商品が届かないケースの中には、もともと商品を販売する(引き渡す)つもりがないと考えられる詐欺的なサイトがあります。また、メーカーの公式サイトを模倣して公式サイトにみせかけている偽サイトや、模倣品を販売しているサイトなどもあります。
これらの悪質な通販サイトで注文してしまうと事業者と連絡がとれず、事業者に対応を求めることは困難です。
(2)注文前のサイトの見極め
このようなサイトには次のような特徴がみられます。注文する前に、信頼できるサイトかどうか十分に確認してください。
- サイト内の日本語が正しく表記されていない
- 市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている
- ブランド、メーカー品で価格が通常より安い
- 支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である
- キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない
- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない など
(なお、これらの特徴に当てはまらなければ安全ということではありません。)
CCJでは、2024年6月から、寄せられた相談を調査して、悪質通販サイト情報を公表しています。
また、日本サイバー犯罪対策センターがサイトで紹介している詐欺サイトチェッカー(SAGICHECK)などを利用するのもよいでしょう。
(3)模倣品の水際取締り強化
関税法等の改正により、2022年10月より税関での取締りが強化されました。海外事業者が運営するサイトで注文した場合、商品が海外から届くケースが多いと思われますが、模倣品の疑いがある場合は、税関で商品が止められ模倣品かどうかの認定手続が開始されます。模倣品と認定された場合は、個人利用目的であっても税関で没収され、消費者の手元に商品は届きません。
詳細は税関のサイトを参照ください。
(4)最近流行している手口に注意
「スタート」ボタンの広告で誘導する海外サブスクサービスサイト
国内事業者のサイトを利用しようとして表示された「スタート」等のボタンをクリックし、表示された画面にクレジットカード情報等を入力したところ、海外事業者のゲーム配信サービスなどのサブスクリプション契約を締結したことになっていた、という相談が多く寄せられています。「スタート」等のボタンは実は広告で、クリックすることで、広告主のサービスに登録する画面に遷移するようになっています。
オンラインストレージサービスを利用しようとした際や2次元コードを読み取る際など、様々な場面で、この手口の広告が表示されており、注意が必要です。
5トラブルに遭ってしまったら
(1)支払手段別の対応方法
悪質な海外通販サイトで「商品が届かない」等のトラブルに遭った場合、対応方法は支払手段によって異なります。
- ① 銀行振込の場合で振込み前であれば、絶対に振り込まないでください。
- ② 銀行振込をしてしまった場合は、振込先銀行に「振り込め詐欺救済法」の申し出をしましょう。この法律は、詐欺などの犯罪に使われた口座を金融機関が凍結し、その口座の残高から被害回復分配金として、被害額に応じて被害者に支払いがなされる手続等を定めています。なお、凍結を行うかは銀行の判断となります。また、凍結されても被害金額全額が戻ってくるとは限りません。
- ③ クレジットカード払いの場合は、カード会社に状況をよく説明して相談しましょう。VISAやMasterなどの国際ブランドの自主ルールであるチャージバックという仕組みによって、決済金額が返金される可能性があります。そのルールが適用されるかどうかはカード会社の判断になります。また、支払いに使用したカード番号の変更についても相談するとよいでしょう。
(2)事業者への連絡
事業者には解約(キャンセル)することをメール等で連絡しましょう。特にサブスクリプション契約となっている場合、解約しないと利用の有無にかかわらず定期的に料金が課金されてしまいます。海外事業者には英文で解約を申し出るとよいでしょう。
CCJのサイトでは解約申立てのための英文テンプレートを掲載していますので参考にしてください。
(3)ショッピングモールを利用した場合
ショッピングモール(デジタルプラットフォーム)内の店舗で商品を購入した場合、モール運営事業者(プラットフォーマー)が補償制度を設けている場合があります。
また、ショッピングモールでのアカウント等から販売事業者(モール内店舗)に連絡がとれる等の仕組みとなっているものもあります。
さらに、販売事業者と連絡がとれない場合は、モール運営事業者に対して販売事業者の連絡先を開示するよう請求できます(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF法)5条)。また、個別の被害救済を求められるものではありませんが、適切な措置を採るよう内閣総理大臣(消費者庁)に申し出ることができます(同法10条)。申出は消費者庁サイトからできます。
6海外事業者との契約に適用される法律
(1)準拠法 日本法の適用
海外事業者との取引について、どの法律に準拠(適用)して考えればいいのでしょうか。これについては、利用規約などに、事業者所在地の法律が適用されると記載があり、サイトを利用する際に利用規約に同意していることが多いと思います。しかし、「法の適用に関する通則法」11条に「消費者契約の特例」が規定されており、この規定により、日本の消費者が日本法の適用を主張できる場合があります。
(2)基本の考え方
インターネットで行った商品購入やサービスの申込みなどの取引は、他の契約と同様に双方の意思の合致(申込みとその承諾)で成立します。インターネット取引の場合、インターネット上で、契約の内容や条件(「利用規約」「返品返金」「キャンセル料」などの項目で記載されていることがあります)が示され、それに「同意」する形で、その契約内容に合意することが多いと思います。
(3)特定商取引法上の通信販売
A. 物販の契約のキャンセル(返品返金)
前述のように日本語表示のサイトの場合は、特定商取引法の通信販売の規定が適用されると考えられます。この規定では次のように定めています。①事業者が返品特約(返品のルール)を定めてサイトに表示している場合は、それが適用される。②事業者が返品特約をサイトに表示していない場合は、商品の引き渡しを受けた日を含めて8日以内なら契約の撤回や解除(キャンセル)ができる(この場合には返品返金を双方がそれぞれ行うことになります)。
なお、これは特定商取引法のクーリング・オフ制度とは異なるものであり、通信販売にはクーリング・オフ制度はないことに注意しましょう。
B. 申込みの取消し
特定商取引法の通信販売では、申込みを確定する前に、その内容や代金等を確認できる最終確認画面の表示が事業者に義務付けられています。また、法定の表示項目が不十分である等のために消費者が誤認して申し込んだ場合、申込みを取り消すことができます。(特定商取引法12条の6、15条の4)
(4)消費者契約法
不当な勧誘を受けて契約してしまった場合の取消権や消費者の利益を不当に制限する契約条項の無効が定められています。
(5)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(電子契約法)
インターネットで消費者が操作ミスをして申込みしてしまった場合、取消しできる場合があります。しかし、事業者が最終確認画面を表示していれば、事業者は契約の有効性を主張できます。(電子契約法3条、民法95条3項)
(6)未成年者取消し
成人は自分の意思で契約ができます。一方、未成年者(18歳未満)が契約するには親の同意が必要で、これを得ずに契約した場合には、取り消すことができます(民法4条、5条)。しかし、事業者に成人であると嘘をつくなどした場合は取消しができません(同法21条)。海外事業者に限らず、オンラインゲームの利用(課金)などで問題になりやすい点です。
(7)まとめ
海外事業者においては日本法の制度の認知や理解が十分とは言えない場合があります。また、取消しや無効の主張は、事実の当てはめ等をしっかり行う必要があることなどから、消費者が海外事業者に単独で取消しや無効の主張を行うことは非常に難易度が高いと言えます。
7生徒に伝えてほしいこと
インターネット通販では、簡単に商品の購入やサービスの利用ができますが、それは全て事業者と契約を結んでいるということです。一般的には、その契約の内容はインターネット上に記載されていて、取引の際にその内容に利用者は合意をしています。分かりやすく言えば、誰も詳しく説明をしてくれないが、自分で契約内容を理解し、自己責任でその契約内容にOKしている、ということです。
また、無料サービスを利用すると、広告やおすすめが表示され、リンクから申込み画面に飛べるものもありますが、インターネット上の情報の中には悪質通販サイトも紛れています。
タイパ(タイムパフォーマンス)が重視される時代ですが、急がずひとつひとつ確認しながらインターネット通販を利用し、少しでも分からないことがあったり不安に思ったりしたら手続を止めて、周囲の人や消費生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン「188(いやや)」では、最寄りの消費生活センター等を電話でご案内しています。
また、海外事業者とのトラブルについては、CCJでも受け付けています。

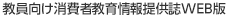
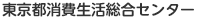 Copyright Tokyo Metropolitan Government.
Copyright Tokyo Metropolitan Government.